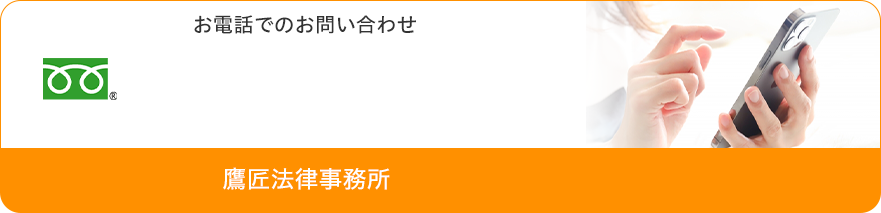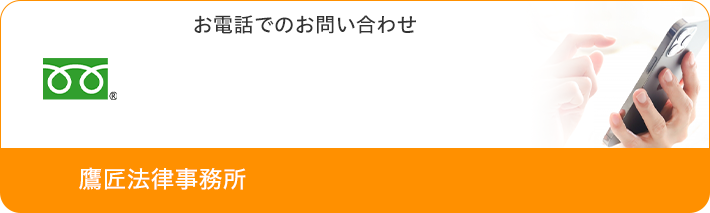はじめに
最近、被相続人の相続人が全く不存在である相続事例を当事務所でも取り扱っています。
相続人がいない(不存在)場合、その被相続人の遺産はどうなってしまうのでしょうか。
相続人がいない場合、一般的にその被相続人の遺産は国庫(国)に帰属することになりますが、この遺産を誰かに相続させたり、国庫ではなく福祉団体に渡すことはできないでしょうか。
ここでは相続人がいない(不存在)場合の遺産の行方や、その遺産処理の手続の概要について説明します。
相続人がいない(不存在)とは、どんな状態か。
一般的には、被相続人が死亡した場合、相続が開始し、遺産は相続人が相続することになります。
しかし、身寄りのない高齢者が死亡した場合など、被相続人に相続人が一人もいないこともあります。
このように相続人が一人もいない状態のことを相続人不存在の状態といいます。
相続人がいない(不存在)場合、相続開始時に被相続人が有していた遺産は国庫、すなわち国の財産になります。
毎年、相続人不存在によって、国庫に帰属する額は600億円以上にもなるといわれています。
3 相続人がいない(不存在)状態になる事例
相続人がいない(不存在)状態になるのは、次のような事例が考えられます。
- そもそも法定相続人が誰もいない。
- 相続人はいるが、相続放棄を家庭裁判所に申述することによって相続人がいなくなった。
- 相続人に欠格事由があり、もしくは相続廃除により相続人がいなくなった。
(1) そもそも法定相続人がいない事例
相続人不存在として典型的な事例は、両親も、夫や妻も、子供も兄弟姉妹もいない場合です。
又、被相続人が死亡し、相続が開始した時に、既に両親、配偶者、子供、兄弟姉妹等の推定相続人が全て死亡していた場合も、その典型的事例です。
被相続人が高齢である時、このような事態がよくみられます。
(2) 相続放棄により相続人がいない事例
法定相続人が存在しても、法定相続人の全てが相続放棄してしまった場合、相続人は不存在となります。
相続放棄とは、法定相続人が家庭裁判所に相続の放棄を申述した場合です。
相続をする場合、不動産や動産、預貯金、株式等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの負債も相続することになります。
プラスの財産があったとしても、借金等の負債がそれを上回る場合、相続人は相続の放棄をする人が多いです。
相続の放棄をすると、その法定相続人は遺産分割の協議に全く参加することができません。
そのため、法定相続人全員が相続の放棄をすると相続人不存在の状態となります。
(3) 相続人欠格、廃除により相続人がいなくなる事例
法定相続人が存在しても、相続できない場合として、上記の相続放棄以外に民法上、相続人欠格や廃除の制度が定められています。
欠格とは、被相続人を殺したり、被相続人を強迫して遺言をさせるような、相続に関する法律に違背する行為をした者が法定相続人の資格を奪われることをいいます。
又、廃除とは、法定相続人が被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行をした場合に、被相続人の意思によって、その法定相続人の相続人としての地位を奪ってしまうことです。
相続人欠格、廃除により、法定相続人が一人もいなくなった場合も相続人不存在の状態となります。
相続人不存在の場合の遺産の行方
上記のような事由で相続人がいない(不存在)場合、被相続人の遺産はどのようになるのでしょうか。
(1) 遺言書により遺贈がなされている場合
被相続人が生前、遺言書を作成していて、その中で特定の者に対して遺産を贈与することが書かれていた場合、遺産はその特定の者に帰属することになります。
遺贈を受ける者は、個人でも法人でもよいので、生前に世話になった知人や友人に遺贈されることもよくみられます。
又、福祉団体に寄付として遺贈されることもあります。
(2) 特別縁故者がいる場合
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合、被相続人と特別な縁があったことを理由に遺産を受け取る権利が発生する者のことです。
被相続人と生計を共にしていた、又、特別に親しい間柄にあった等、家庭裁判所によって、相当の関係があると認定された場合に特別縁故者となります。
特別縁故者と認定されると、遺産の全部、又は一部を分与されることになります。
特別縁故者として、被相続人の遺産の分与を考えている者は、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立て等をして、分与の手続をとらなければなりません。
(3) 遺贈がなく、特別縁故者もいない場合
このように、被相続人が遺言書による遺贈がない場合や特別縁故者もいない場合には、遺産は国庫に帰属し、国の所有に帰します。
なお、特別縁故者がいた場合でも、その特別縁故者に対して、家庭裁判所が一部の財産しか分与しないこともあります。
その場合、分与されない遺産は国庫に帰属し、国の所有に帰します。
相続人不存在の場合の手続の概要
相続人が不存在の場合、利害関係人、又は検察官が相続財産清算人選任を家庭裁判所に申立てることになります。
家庭裁判所に選任された相続財産清算人は、被相続人の遺産の管理、処分を行います。
(1) 相続財産清算人の選任と相続人捜索の公告
家庭裁判所は、相続財産清算人の選任をしたこと、及び被相続人の相続人がいる場合には申し出るようにとの公告をします。
相続人捜索の公告は、民法により6か月以上の期間を定めなければならず、この期間内に相続人が申出た場合には、遺産はその相続人に交付されることになり、相続財産の手続は終了します。
(2) 債権申出の公告
家庭裁判所は、(1)の公告に加え、被相続人に対する債権者や受遺者がいる場合には、届出るように公告します。
この届出については、2か月以上の期間が定められます。
期間満了後、届出のあった債権者と受遺者に対して遺産から弁済がなされます。
この弁済により、遺産が全てなくなった場合には、相続財産手続は終了します。
(3) 相続人不存在の確定
相続人捜索の公告期間が満了し、この期間内に相続人が申出なかった場合、相続人不存在が確定します。
確定までの期間は最短でも6か月ということになります。
特別縁故者の財産分与の申立て
自分が特別縁故者に該当すると主張する者は、相続人不存在が確定してから3か月以内に家庭裁判所に対し、財産分与の申立てしなければなりません。
家庭裁判所は、審判により、申立人が本当に特別縁故者に該当するか否か、財産の分与が相当であるとされた場合、分与額はいくらが妥当かを判断します。
この財産分与の審判が確定すると、相続財産清算人は、特別縁故者と認定された者に財産を分与することになります。
相続財産清算人対する報酬が支払われた後に、残余財産があった場合、相続財産清算人は、それを国庫に帰属させる手続を行い、任務が終了ることになります。
まとめ
相続人がいない(不存在)場合の遺産の処理は上記のとおりとなります。
被相続人と交流のあった方で、自分が特別縁故者に該当しているか否かで迷っている方もいると思います。
当事務所は50年以上の古い歴史を有し、今までに相続人不存在の場合の遺産の処理や、特別縁故者への財産分与の申立てを数多く担当してきています。
上記のことで相談したい方は、相談料は無料ですので、当事務所にお気軽にご連絡いただければ幸いです。