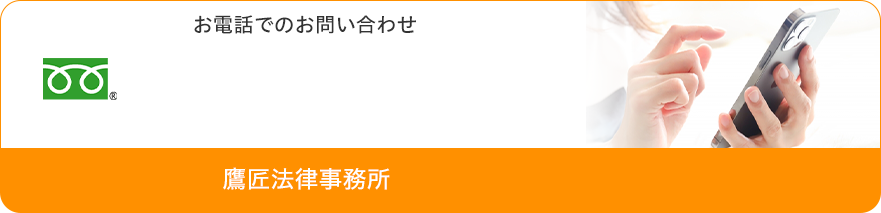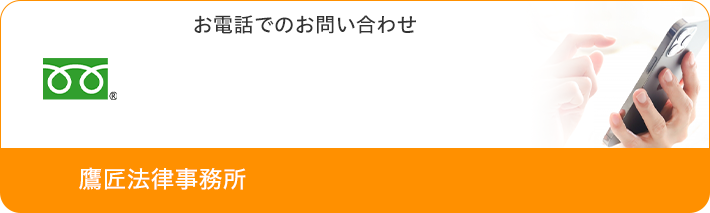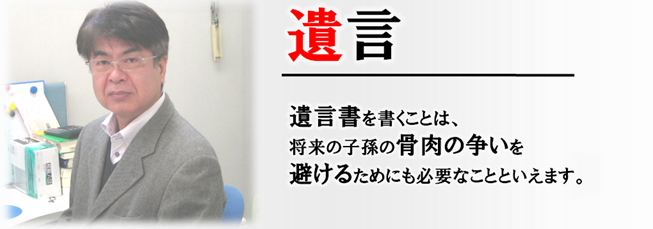
遺言につき,民法は,遺留分という制限はありますが,原則,被相続人の意思,すなわち,遺言書のとおり相続が行われることを認めています。そのため,遺言書の有無は,相続手続きを進めて行く上で,重要となります。
遺言がない場合のデメリット
遺言がない場合,共同相続人全員の協議(合意)により遺産を分割する必要があります。ただ、共同相続人間に経済的格差がある場合,遺産が不動産や証券など多岐に渡る場合など「争族」となってしまうこともあります。
また,相続人の数が多い,相続人が海外など遠方に住んでいる,相続人間の仲が悪い,行方不明者の相続人が居るなどの事情がある場合,遺産分割協議が進まないこともあります。
被相続人に子がいない場合,相続人は,配偶者の他,被相続人の両親,兄弟姉妹となりますが,これらの相続人が被相続人とその配偶者が築いてきた遺産を相続することに納得できないと感じることもがあります。
被相続人が,生前にお世話になった相続人でない人に遺産を残したいと考えていても,被相続人の意思を実現することが確実であるとは言えません。
遺言の方式
このようなデメリットを回避できる遺言ですが、その作成方式は民法で定められていて、その方式に違反すると無効となってしまいます。また、遺言の種類についても複数あり、①公正証書遺言 ②自筆証書遺言 の2種類があります。ただ、公正証書遺言は,原則公証人役場において,遺言の内容を公証人及び2名の証人の前で申し述べ,公証人が遺言書を作成するもので、作成方式に違反することはありません。
そこで、もう一つの遺言書、自筆証書遺言について、以下説明します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言には、令和2年7月から法務局で保管制度が始まり、その制度を利用した遺言書と、利用していない遺言書があります。法務局の保管制度を利用した場合は、法務局の職員が自筆証書遺言の方式をチェックしてくれますので、作成方式に違反することめったにありません。
保管制度を利用していない自筆証書遺言
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で遺言書を作成し,日付・氏名を記入の上,押印して作成する遺言書です。
なお,令和元年1月から「財産目録」を別紙として添付する方式をとれば相続財産を自筆で書くことは不要となり,パソコン・代筆・通帳や不動産登記簿謄本のコピーを別紙1,別紙2として添付すればよくなりました。ただ,偽造防止のために「財産目録」のすべてのページに署名・押印が必要です。
自筆証書遺言の書き方
遺言は法律で作成の仕方が定められており、定められた様式に則って作成しなければなりません。作成の仕方は遺言の方式によっても異なりますので、注意が必要です。
以下では自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をさせて頂きますが、遺言書の作成に当たっては弁護士などの専門家に相談することをお勧め致します。
自筆遺言作成のポイント
1.全文を自筆で書くこと。
2.用紙は自由。
3.縦書き、横書きは特段の制約はなし。
4.筆記具は自由(ボールペン、 万年筆等制限はありません)
5.日付を自筆で記入すること。
6.氏名を自筆で記入すること。
7.捺印をすること(認印や三文判でも構いませんが、実印が好ましい)
8.修正・変更する場合には当該箇所に押印し、その上部に修正・変更の箇所と内容を付記し、署名すること。
自筆証書遺言の注意点
日付、署名、押印のない遺言書は無効
これらのない遺言書は、無効となります。
特に、「日付」ですが、遺言書はいつでも撤回ができ、その場合、日付の新しいものが優先するため「日付」の記載は重要です。
また、日付が特定できない(例えば、令和7年3月、令和7年3月吉日等)場合も、同様の理由で無効となります。
加除訂正
自筆証書遺言は「遺言者が自筆で遺言書を作成」することが必要なので、間違うことがあります。その場合、改めて遺言書を作成するか、間違えた遺言書に加除訂正します。
この加除訂正は、民法に従って,行う必要があり、それに違反すると自筆遺言証書は無効となってしまいます。
この加除訂正の手順は次のとおりです。
ア 訂正箇所を2本の線で消し,変更する文字を記入します。
イ 訂正箇所に押印します(遺言書の押印と同一の印を使います)
ウ 訂正箇所の欄外に「この行,何文字削除・何文字加入」と記入するか,遺言書の末尾に「何行目「●●●」とあるのを「〇〇〇」と訂正した」と記入します。
エ 訂正の記入後に署名します。
不明確な遺言
自筆証書遺言は、検認手続きを経て、この遺言書に基づき、金融機関、法務局等で名義変更等の手続きを行うため、特に「財産目録」について明確な記載が求められます。
「預金」については、金融機関名、支店名、種類の別、口座番号を、不動産については、不動産登記簿謄本の記載のとおり、所在、地番、地目、地積等を記載してください。
夫婦共同遺言
仲の良い夫婦が、夫が先に亡くなったら妻に、妻が先に亡くなったら夫に相続させるという遺言を1通の自筆証書遺言で作成すると無効になります。
このような遺言が無効となるのは、複雑な法律関係を避けること、1通だと遺言者(例えば、妻)が相手方(夫)の遺言に拘束され自由に撤回できなくなるからです。夫婦が遺言書を作成するには、別々に作成してください。
まとめ
死亡後、自分の意思を相続人に伝えたい、「争族」を避けたい、そのために公正証書遺言、自筆証書遺言を作成したいとお考えの方は、一度当事務所にご相談ください。
50年以上の歴史を有する当事務所は、遺言書に関する知見も蓄積されており、きっとあなたの意思に沿った遺言書の作成ができるものと思います。