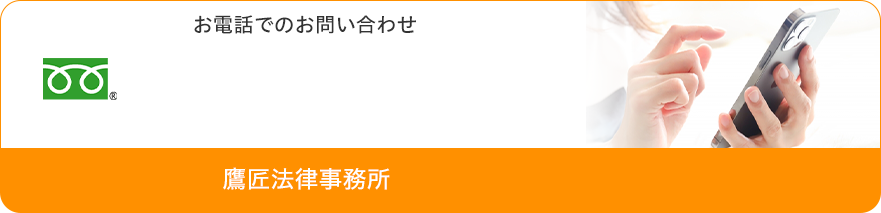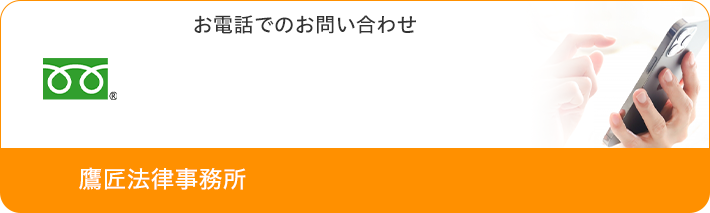遺産相続トラブルは調停・審判にて解決
遺産分割協議
相続は死亡によって開始します。そして、相続人は、被相続人の財産を承継します。相続人が複数人いる時は、相続財産は、相続人の共有になります。この相続財産の共有状態を解消し、個々の財産を相続人に分ける手続きが遺産分割協議です。
被相続人が遺言書を残し、その遺言で遺産の分割方法を指定している場合は、相続人は、その指定に従って遺産を相続します。
遺言がない場合、相続人は話し合いをして、遺産を分割します。
この手続きを遺産分割協議といい、この話し合いがまとまらない場合は、相続人は他の相続人を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることになります。
遺産分割調停
遺産分割調停
遺産分割調停は、公正中立な調停委員に入ってもらい、相続人が話し合いで遺産分割の合意をする手続きです。
調停では、公正中立な立場の調停委員が各相続人の意向を聞き、解決案を提示したり、助言をしたりして、相続人が合意に至るよう話し合いを進めます。
この調停において、全ての相続人が遺産分割内容に合意すると、調停調書が作成されます。この調停調書は確定判決と同一の効力をもちます。
調停申立ての準備
遺産分割調停申立書の提出
調停申立てをする場合、家庭裁判所へ、遺産分割調停申立書を提出します。
この申立書には、「被相続人」「当事者(相続人)」「申立の趣旨」「申立の実情」「遺産目録」を記載します。
申立の趣旨には「被相続人の遺産の分割を求める」との記載で十分です。
遺産目録は、被相続人にどのような遺産があったのか、例えば不動産、預貯金、株式等を示す遺産の目録です。
添付書類の用意・提出
調停申立書の他に、調停に必要となる資料も提出します。
相続関係図
当事者に関する資料で、申立人と相手方の戸籍謄本、住民票、被相続人が生まれてから死亡するまでの原戸籍謄本、除籍謄本、住民票等が必要です。
遺産分割の査定に必要な資料
遺産に不動産が含まれていれば、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書等が必要です・
また、預貯金、株式等があれば、その残高証明書を用意する必要があります。もし、被相続人に借金があれば、その取引履歴も必要です。
収入印紙等
調停申立書は、手数料額の収入印紙を貼って提出します。被相続人1名につき1200円です。
また、家庭裁判所から相手方へ郵送するための郵便切手が必要となりますが、その金額は家庭裁判所で異なりますので、問い合わせてください。
調停手続き
調停申立後、家庭裁判所から調停期日の連絡があります。調停当日は、待合室で待機していると、調停委員が呼びに来て、調停室に案内されます。待合室は、申立人側と相手側の2部屋がありますので、待合室で顔を合わせることはありません。
最近では、家庭裁判所に出頭しなくてもテレビ(Web)会議で開催されることも多く、当事者や代理人はとても便利になっています。
このような調停は、おおよそ月1回のペースで進行します。合意の成立まで要する日数は事案次第で、早ければ3回ほど、事案によっては数年を要することがあります。
調停の争点の検討順序
遺産分割調停の争点の確認、検討には、次のような順序があり、これらの争点につき合意ができると調停が成立します。
- 遺言書はあるか。
- 相続人は誰か。
- 遺産分割の対象となる遺産は何か。
- 不動産等金銭に換算した場合の評価額はいくらか。
- 各相続人の具体的な相続割合はどうか。
- 遺産をどのように各相続人に分配するか。
遺産分割調停での話し合いがまとまらない場合(調停不成立)
このような場合には、自動的に遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判
遺産分割審判は、担当裁判官が単独で、申立人、相手方(以下「当事者」といいます)の主張や提出された資料に基づいて、遺産分割方法について判断し、決定する手続きです。
事実調査及び証拠調べ
担当裁判官は、職権で、事実の調査及び必要と認める証拠調べをしなければならず、当事者は、これに協力しなければなりません。
事実の調査は、審判をするのに必要な資料の収集をすることで、具体的には、当事者、参考人等の審問が中心となります。この手続きは、当事者出席の場で行われます。
また、当事者は、担当裁判官に対し、必要と認める証拠調べを求めることができます。当事者としては、有利な審判を求めるため、積極的に証人尋問の申立てなどをし、有利な事実を証明することになります。
遺産分割の方法の検討
遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割等の方法がありますが、担当裁判官は、一切の事情を考慮して裁量的に審判をします。
具体的には、当事者の取得すべき遺産の金額を前提とし、遺産である家屋に居住しているかどうか、家業や農業を承継しているかどうか、会社の後継ぎかどうかなどを考慮して審判がなされます。
この審判に納得できない場合は、審判書の告知を受けた翌日から2週間以内に不服の申立て(即時抗告)ができます。
この期間内に即時抗告をしないと、この審判は確定します。
まとめ
当事務所は50年以上の歴史を有し、今までに数多くの遺産分割事件を取り扱ってきました。
当事務所には数多くの解決例と経験が蓄積されていますので、遺産分割でお悩みの方はお気軽に当事務所にご連絡下さい。
遺産相続トラブルについては、まずは当事務所にご相談ください。初回相談は、無料にて応じています。